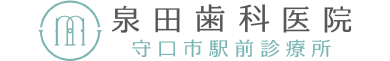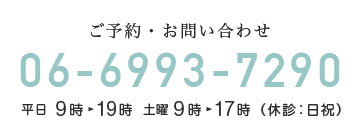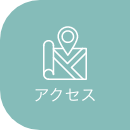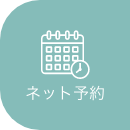三叉神経痛
三叉神経(さんさしんけい)は顔や歯の感覚(痛覚・触覚・温覚など)を脳に伝える神経ですが、この神経に支配されている部位に起こる痛みを三叉神経痛といいます。脳・赤津伊神経など中枢神経に関連して起こる本能性三叉神経痛と、末梢領域のいろいろな原因によって二次的におこる症候性三叉神経痛とがあります。
 本能性三叉神経痛は最近、頭がい内で三叉神経に、動脈硬化などで屈曲した動脈や静脈が直接ぶつかり、圧迫することによって生じることが明らかになってきました。また、脳腫瘍が三叉神経を圧迫または癒着することによっても起こるといわれています。一方、症候性三叉神経痛は、歯や副鼻腔などの疾患が原因で引き起こされます。
本能性三叉神経痛は最近、頭がい内で三叉神経に、動脈硬化などで屈曲した動脈や静脈が直接ぶつかり、圧迫することによって生じることが明らかになってきました。また、脳腫瘍が三叉神経を圧迫または癒着することによっても起こるといわれています。一方、症候性三叉神経痛は、歯や副鼻腔などの疾患が原因で引き起こされます。
本能性か症候性かにかかわらず、通常痛みは顔面や口腔の左右どちらかにみられます。三叉神経の三つの枝(眼神経、上顎神経、下顎神経)のどれが関与しているかによって痛みの部位は異なりますが、本能性では突然、電撃のような激しい痛みがあるのが特徴です。この痛みは短時間(数秒から30秒ぐらい)で治りますが、繰り返し起こります。
発作は、食べている時、洗顔、ひげそり、歯みがき、会話などの刺激で誘発され、特定の部位にが引き金となっています。時には風に当たっただけで痛むこともあります。一方、症候性の痛みは電撃様ではなく、範囲や程度もさまざまですが、初発年齢は40歳以上であることが多いようです。
三叉神経痛が疑われた場合、まずMRI(磁気共鳴画像化装置)などによる画像診断が必要です。症候性では原因を精査し、判明すればその治療を行うとで改善していきます。本能性の治療法には大きく分けて、内服薬による治療(軽症例に対しては抗てんかん薬カルバマゼピンが特効薬)・神経ブロックによる治療・ガンマ―ナイフによる放射線治療・頭がい内における三叉神経の減圧手術(ジャネッタ手術)、の四つがあります。
口腔顔面痛の診断には歯科の領域の中でも、さまざまな方面からのアプローチが必要な分野です。脳神経外科、神経内科、麻酔科(ペインクリニック)、心療内科などの換券する各科と密な連携を取り、診断して治療を行う必要があります。気になる方は、かかりつけ医への相談をお勧めします。
口腔顔面痛
 近年は高齢社会、ストレス社会といわれています。それに伴って、口腔鰐顔面領域においても、ストレスとの関連が指摘されている疼痛を訴える患者さんが増えております。口腔顔面痛の診断には、歯科の領域の中でもさまざまな方面からのアプローチが必要です。脳神経外科、神経内科、麻酔科(ペインクリニック)、心療内科などと連携を密にして診断し、治療を行う必要があります。
近年は高齢社会、ストレス社会といわれています。それに伴って、口腔鰐顔面領域においても、ストレスとの関連が指摘されている疼痛を訴える患者さんが増えております。口腔顔面痛の診断には、歯科の領域の中でもさまざまな方面からのアプローチが必要です。脳神経外科、神経内科、麻酔科(ペインクリニック)、心療内科などと連携を密にして診断し、治療を行う必要があります。
口腔顔面領域の痛みで最も頻度高いのが、歯肉の炎症やむし歯の痛みで、通常は歯科治療で徐々に治まってきます。しかし、「顎の間接が痛くて口が開きにくい」「歯の神経を抜いたのにまだしみて痛い」「顔を洗ったり、ひげをそると痛みが走る」「食事をしていないときも、舌がヒリヒリする」など、通常の歯科治療で治らない痛みがあります。その代表的なものは、顎関節症、非定型顔面痛・歯痛、三叉神経痛、舌痛症などが挙げられます。まず、舌痛症について説明いたします。
視診や触診などで舌や歯に炎症や腫れなどの異常が認められないのに、舌が一日中ヒリヒリしたり、擦り切れるような痛み、しびれたような、やけどの後のような違和感が数カ月~数年続く、舌の慢性的な痛みを舌痛症といいます。何かに熱中している時には痛みを忘れていることもありますが、逆に何もしていない時や寝る前に痛みを強く感じたりします。また、食事や会話には支障がないことも多く、特に40歳以上の女性に多い症状です。
原因はまだ解明されていません。痛みを伝達し知覚する神経回路に障害が生じているのではないか、心理・社会的な要因が関係しているのではないか、舌粘膜の抵抗性の減弱ではないかという説などがあります。歯の鋭端や入れ歯などが合わず舌を刺激しているため痛む場合や、むし歯治療の時にかぶせた金属へのアレルギーが原因の場合もあります。
治療は類似の症状をの示す疾患(口腔カンジタ症、口腔乾燥症、貧血、亜鉛や銅の不足)の影響を判断するため、まず検査をし、疾患の影響があればその治療をします。また、歯や入れ歯の鋭縁などの局所的な原因の除去や口腔ケア(歯石の除去など)を行います。そして、個々の患者さんに応じて、うがい薬、漢方薬、抗うつ薬などの薬物療法を行います。短期間で治ることは難しいですが、あまり心配せず、根気良く治療していく努力が必要です。心療内科と連携し、歯科医師とともに心身両面からの治療をするのが理想と思われます。