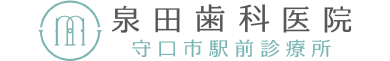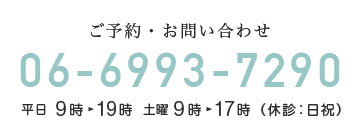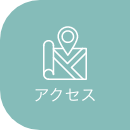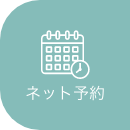今回は、お子様の虫歯と治療方法についてご説明します。ご参考になりましたら幸いです。
どんなに丁寧に歯磨きをしていても、子どもの虫歯を完全に防ぐのは簡単ではありません。実際、幼児期の虫歯は多くの家庭で見られる問題のひとつです。
子どもの歯は大人の歯と構造が異なり、虫歯になりやすい要素が揃っています。また、虫歯の進行具合や症状の現れ方も大人とは異なるため、気づいたときにはすでに状態が悪化しているケースも少なくありません。
今回は、子どもの虫歯が大人とどう違うのか、虫歯になった場合にどのような治療が行われるのか、さらに何歳から治療を受けられるのかといった点について、わかりやすくご紹介します。
■子どもの虫歯に見られる特徴とリスク
 子どもの虫歯には、主に4つの大きな特徴があります。まず、虫歯の進行が非常に速いという点です。乳歯は永久歯と比較してエナメル質が薄く、細菌による酸で溶けやすいため、虫歯になるとあっという間に象牙質や神経にまで進行してしまうことがあります。
子どもの虫歯には、主に4つの大きな特徴があります。まず、虫歯の進行が非常に速いという点です。乳歯は永久歯と比較してエナメル質が薄く、細菌による酸で溶けやすいため、虫歯になるとあっという間に象牙質や神経にまで進行してしまうことがあります。
次に、乳歯の虫歯は見た目だけでは判断がつきにくいことが挙げられます。大人の虫歯は黒くなったり茶色く変色したりしますが、子どもの場合は表面が白く濁る程度の変化しか見られないことも多く、気づかれにくいのが実情です。
さらに、乳歯が虫歯になって早期に抜けてしまうと、その後に生えてくる永久歯の位置や歯並びに悪影響を与える恐れがあります。歯の隙間が不自然に狭くなる、噛み合わせがずれるなどの可能性もあります。
そしてもう一つ重要なのが、子どもは虫歯による痛みを自覚しづらいという点です。神経が未発達な段階では、痛みを感じにくかったり、痛みをうまく言葉にできなかったりすることがあります。そのため、保護者が見落としてしまうこともあるのです。
■虫歯の進行段階ごとの治療内容
子どもの虫歯治療は、進行状況によって治療方法が変わります。初期の虫歯(エナメル質が少し溶け始めた段階)であれば削る必要はなく、フッ素を塗布して歯の再石灰化を促す方法が用いられます。歯磨きの仕方や生活習慣を見直すことで、虫歯の進行を止めることも可能です。
次の段階である、歯に小さな穴が空いた状態では、虫歯部分を最小限に削り、歯科用のレジン(樹脂)で埋める治療が行われます。これは1回の通院で済むことが多く、子どもにとっても比較的負担の少ない治療です。
虫歯がさらに進行し象牙質に達すると、冷たいものがしみたり、痛みを感じたりするようになります。この場合は、虫歯部分を丁寧に削ったうえで、詰め物を作って修復します。ここまで進行していると、複数回の通院が必要になることもあります。
さらに悪化して神経まで虫歯が到達してしまうと、強い痛みや歯ぐきの腫れなどが現れることがあります。この段階では「根管治療(こんかんちりょう)」と呼ばれる神経の処置が必要ですが、子どもの場合は成長を考慮して、神経をすべて除去せず一部を残す「生活歯髄療法(せいかつしずいりょうほう)」が選ばれることもあります。
そして最終段階になると、歯の大部分が溶けてしまい、歯根だけが残るケースもあります。このような場合には、抜歯が必要になります。
ただし、乳歯を早期に失うと、将来生えてくる永久歯のスペースが足りなくなる恐れがあるため、抜歯後は「スペースメンテナー」という装置を使って、歯並びが崩れないように対応することがあります。
■虫歯治療は何歳から受けられる?
では、子どもは何歳頃から虫歯治療を受けられるのでしょうか?
 実際には、治療が可能になる年齢の目安は3歳前後とされています。これは、子どもが診察台に座って静かにできるようになる時期であり、治療中もある程度の協力が得られるからです。
実際には、治療が可能になる年齢の目安は3歳前後とされています。これは、子どもが診察台に座って静かにできるようになる時期であり、治療中もある程度の協力が得られるからです。
ただし、子どもの成長や性格によって個人差があるため、2歳でも落ち着いて治療ができる子もいれば、4歳になっても怖がって口を開けられない子もいます。4~5歳になると、歯科医師の説明を理解して治療に前向きに取り組めるようになるケースが増えます。
重要なのは、「虫歯ができたから歯医者に行く」のではなく、「虫歯になる前から歯医者に慣れておく」ことです。歯が生え始める1歳前後から定期的に歯科検診に通うことで、虫歯の早期発見や予防につながるだけでなく、歯科医院の雰囲気に慣れることができ、治療時の不安も軽減されます。